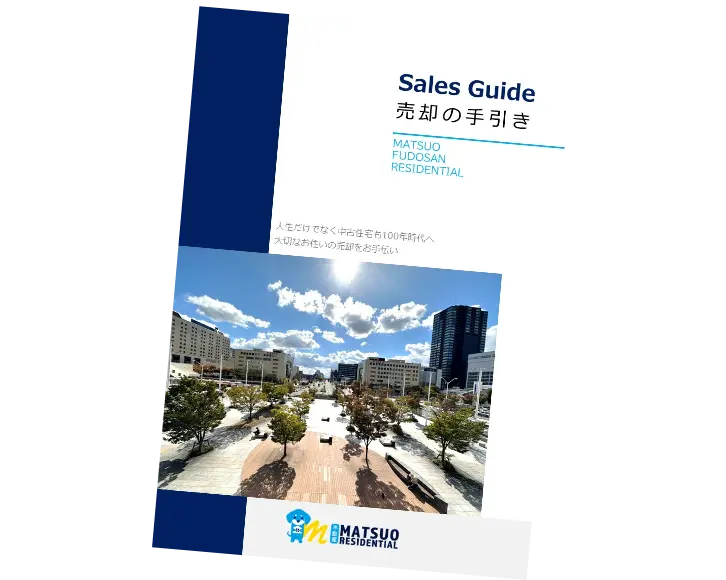
メール又は
郵送でお送りします! Brochure
sell-shisetsu

「親が老人施設に入居することになった」
「親を引き取って同居することにした」……。
そんなとき、いちばんの問題は
「誰も住まなくなった家をどうするか」です。
親名義の家を売るのは、あなた自身が所有者でないこと、また、ご本人が売りたがらないことが多いなど、通常の不動産売買とは異なる点が少なくありません。
では、順を追って見ていきましょう。
第1章そのとき親の家をどうするか、3つの選択
ご家族や親族の誰かがお住まいになる場合を除けば、次の選択が考えられます。
選択1
空き家にする
空き家にしておくという選択は、近い将来、誰かが住む場合を除いてメリットが少ないといっていいでしょう。
メリット
家を所有し続けることができる。
家に戻ることができる。
デメリット
不審者が入りこんだり、放火や不法投棄などの恐れがある。
家屋のいたみや伸びた草木などを手入れする必要がでてくる。
住んでいなくても固定資産税・都市計画税が掛かる。
建物の老朽化により建物価値が下がる。
火災保険を掛けておく必要がある(放火・もらい火リスク)。
ワンポイント
空き家対策特別措置法で「特定空き家」に認定された場合、そのまま放置してしまうと、税金が最大6倍になります。
選択2
賃貸に出す
賃貸契約には、期間を決めて貸す「定期借家契約」と、期間を決めない「普通借家契約」があります。
メリット
借主が見つかれば、定期的な収益が見込める。
家を所有し続けることができる。
デメリット
事前にリフォーム等の費用が必要になる場合がある。
家賃の滞納、家の汚損など、借主とのトラブルの可能性がある。
「普通借家契約」では、自分たちが住みたくなったときに住むことが難しい。
住まなくなってから3年後の年末が過ぎると税優遇を受けられなくなる。
賃貸には2つの契約方法があることを知っておきましょう。
賃貸の期間を定めない「普通借家契約」
自分たちが住みたいタイミングで退去してもらえない可能性があります。反面、借り手が見つかりやすい、賃料が高めに設定できるメリットがあります。
決まった期間だけ貸す「定期借家契約」
契約期間が終われば、確実に退去してもらえる契約です。ただ、借主側にとって条件が悪くなるため、普通借家契約に比べ賃料が低くなる傾向があります。
※賃貸に関わるすべてを一括して業者に任せる「リロケーションサービス」も利用可能です。ただし、管理手数料が家賃の10~15%(通常は5~10%)と高くなってしまうことを知っておきましょう。
選択3
売却する
近い将来、親が家に戻ってくる可能性が少ない—このような最も一般的なケースでは、家の売却が有効な選択肢となります。
メリット
入所前後に売却することで、入所資金の確保に役立てることができる。
売却益を施設の経費や日々の介護に充てることができる。
固定資産税などの税金、メンテナンスの費用や手間から解放される。
相続時に相続人同士が実家売却の話し合いをしなくても済む。
デメリット
親が認知症などの場合、成年後見制度の利用が必要になる。(第2章を参照)
思い出のある親の家に入れなくなる。
第2章親の家を売却するための、必要手続き
家の売却では、ご本人が体力的にも気力的にも低下していることが多く、
ご家族が売却を進めるケースが一般的です。この場合、次の手続きが必要になります。
ケース1
親本人の家を売る意思は明確だが、手続きを進めることが難しい場合
委任状による売却
売却確認時や所有権移転時は本人確認が必要になりますが、本人が署名捺印した「委任状」があると、委任された親族等が「代理人」となり売却の諸手続きを進めることができます。
ワンポイント
委任状に定型のものはありませんが、当社では委任状の要件を満たした書式を用意しております。お気軽にお問い合わせください。
ケース2
認知症などにより、親本人が十分な判断能力に欠ける場合
成年後見制度による売却
家庭裁判所に選任された「成年後見人」が売却を行います。
成年後見人には親族が選ばれるとは限らず、弁護士など第三者が選任されることもあります。
ワンポイント
「成年後見制度」に関しましても、当社にお気軽にお問い合わせください。
第3章早めの売却が、賢い節税につながる
さて、いよいよ売却、そして売買成立のゴールへと進んでいきましょう。
ここでは、家を売る際に、必ず知っておくべき大切なことを見ていきます。
3,000万円特別控除を受けるには、3年以内の売却を。
家の売却後には下記のいずれかの税金がかかります。
「マイホームを売却した場合の特例」の3つの注意点!!